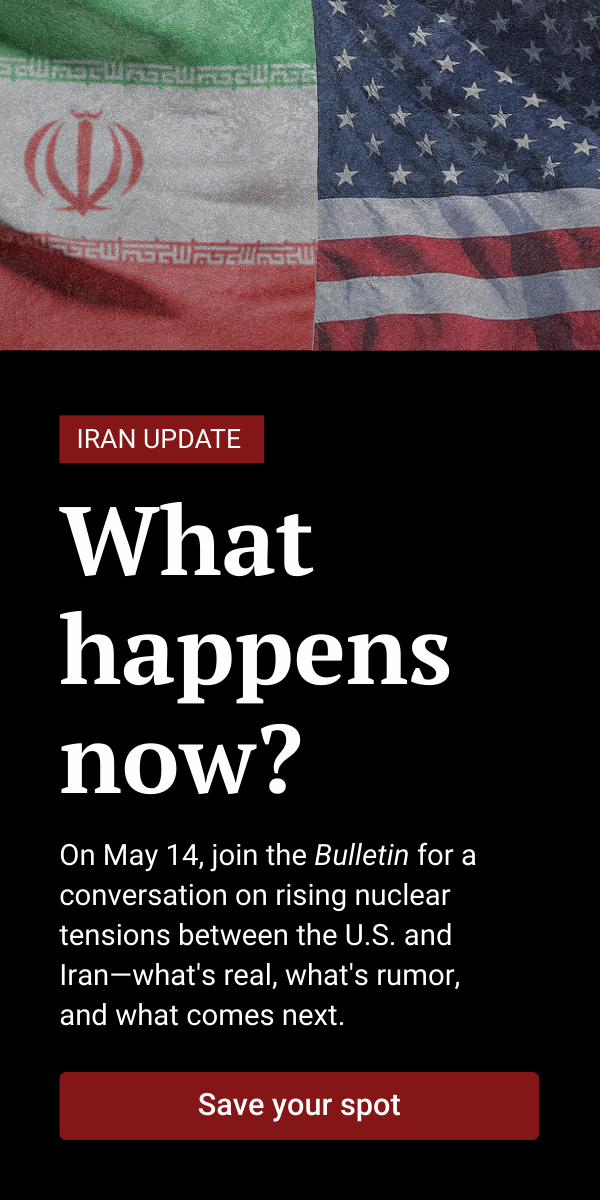ゼロ・リスク思考方法からの脱却 フクシマ後の原発国日本のための教訓と将来の責任
By 鈴木達治郎 (Tatsujiro Suzuki) | September 19, 2011
Article Highlights
福島第一原子力発電所での事故発生から数ヶ月たった今も原子力危機は続いている。峠は越えたように見えるが、多くの技術的・社会的・法的・経済的困難を克服していかなければならない。主要な短期的課題としては、原子炉の安定化、10万トン以上の汚染水の管理、それに、サイト(敷地全体)の除染などがある。サイトには、未だ、事故に起因する大量の汚染されたがれきが残っている。長期的課題としては、貯蔵プールにある使用済み燃料、原子炉内の破損燃料、それに、原子炉の廃炉措置(ディコミッショニング)などがある。国際原子力機関(IAEA)に提出した670ページの報告書において、日本政府は、危機管理のための次のステップを探っている。本稿では、筆者は、福島第一原子力発電所での悲劇を振り返り、政府の計画の中でもっとも緊急の――そしてもっとも難しい――いくつかの点に焦点を合わせる。筆者は、フクシマの教訓は単に日本にとってだけのものではなく、そこから原子力を持っている31カ国すべてが学ぶべきだと論じる。
キーワード
福島第一、過酷事故、水素爆発、IAEA、原子力安全・保安院、全交流電源喪失(SBO)、確率的リスク評価、ゼロ・リスク
3月11日午後2時46分、日本の東北地方において、9.0の地震が、巨大な津波を起こし、これが東京電力の運転する福島第一および第二発電所を襲った。この日は、歴史的な日となった。それは、その規模においても、時間枠的にも、前例のない原子力事故として永遠に記憶にとどまることとなるだろう1。この災害発生から数時間内に、非常用発電機のような技術面から、原子炉への冷却材注入の責任はどの機関にあるのかといった行政問題に至る原子力のインフラに欠陥があり、極めて複雑だということを痛いほど認識させられることになった。
数ヶ月が経過したが、福島第一の状況は、未だに、制御できていない。しかし、最悪の状況は過ぎ去ったようで、放射性物質の放出が再度起こることもなく、また、将来それが起きる可能性もほぼないようである。日本政府は、この事態から学んだ教訓を発表しており、これまでのところ、それに従って対応しているようである。日本政府は、シビア・アクシデント(過酷事故)を防止する――起きた場合にはそれに対応する――ためにもっと強力な手段とシステムを導入すること、原子力緊急事態に対する国の対応措置を定めること、そして、安全規制インフラを強化することを約束した。これらの計画は、日本政府が国際原子力機関(IAEA)に6月に提出した670ページの報告書(原子力災害対策本部、2011年)に示されている。そこにある約束は、日本の原子力の将来のための作業ハンドブックを垣間見させる。日本の原子力の将来は、第二のチェルノブイリ、第二のスリーマイル・アイランド、そして、もちろん第二のフクシマを防ぐために、今も改変・再形成されつつある。
しかし、日本は、フクシマから教訓を見いだし抽出している唯一の国であってはならない。世界の31カ国で合計436基の原子炉が運転されている。世界の原子力コミュニティーや政策決定者らが、これまで得られた情報から学び、今後何ヶ月、何年にも亘ってさらに情報を得る努力を続けることが重要である。既存の原子力施設の安全性を保証し、将来の原子力政策にとっての意味合いを見いだすために、フクシマから教訓を学びとらなければならない2。
シビア・アクシデントの防止
福島第一の事故は、巨大な地震と破壊的な津波の両方によって起きたという点でユニークなものである。地震と津波は、どちらも、設計安全基準を超えていた。設計の段階で、このような事故は、可能ではあるが、ありそうにないとみなされたということである。現在、地震が原子炉の冷却機能の喪失や電源喪失をもたらしたとの証拠はないが、この可能性についても検証をする必要がある。しかし、津波は別だ。津波の高さ――実際に起きたのは10メートル以上――は、日本の規制機関である原子力安全・保安院(NISA)と東電の双方によって過小評価されていた。
2009年6月、地震および津波のリスクについて議論するために開かれた作業部会の会合で、岡村行信(政府の研究者)が次のように述べている。「ここは貞観の津波というか貞観の地震というものがあって、西暦869年でしたか、少なくとも津波に関しては、塩屋崎沖地震とは全く比べ物にならない非常にでかいものが来ているということはもうわかっていて、その調査結果も出ていると思うんですが、それに全く 触れられていないところはどうしてなのかということをお聴きしたいんです。」この研究者は、同氏が委員を務める総合資源エネルギー調査会の新しい報告書が、貞観の津波を十分に検討しなかったことを問題にしているのである。さらに、原子力安全委員会――政府に助言し、原子力安全保安院の活動を監督し、基本的安全指針を設定する――の諮問委員会の元委員石橋克彦も、1997年に『科学』(岩波書店)に掲載された論文で同様の警告を発している。「原発にとって大地震が恐ろしいのは・・・平常時の事故と違って、無数の故障の可能性のいくつもが同時多発することだろう。」(石橋,1997:720-724)
これらの警告は、今、フクシマに照らしてみると、ほとんど予言のように見える。この二人やその他の専門家の意見が真剣にとらえられなかったのは残念である。これらの例は、安全規制過程を再構築する必要があることを示しているが、政府はまだ具体的な勧告をしていない。少数派の意見を如何に組み入れ、最新の情報を反映するかが、解決すべき主要問題であり、効果的に外部電源喪失シナリオに対する計画を立て、シビア・アクシデントの際の冷却機能を確保する上で重要な意味を持つ。
最悪の事態に対する準備
福島第一原子力発電所には、6基の原子炉があり、それぞれ、複数の非常用ディーゼル発電機を備えている。6号機にある非常用ディーゼル発電機の一つをのぞき、6基の原子炉の非常用ディーゼル発電機のすべてが津波でやられてしまった。フクシマの事故があれほどひどいことになったのは、原子炉の冷却に必要な電力供給を確保できなかったからである。
原子力安全委員会の安全設計審査指針において採用されている明確な想定は、一つの原子炉ですべての非常用発電機が使用不能となっても、同じサイト(敷地)の他の原子炉から電力が送られてくるというものである。補助バッテリーの寿命――8時間――は、交流(AC)電源の回復に必要とされる時間と比べると長いもののはずだった。電源は、わずか数時間で回復されると想定されていた。実際、この審査指針は、設計基準事象として、AC電源の完全な喪失を考慮してさえいない――「長期間にわたる全交流動力電源喪失は、送電線の復旧又(また)は非常用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない。」
日本では、確率的安全性評価――別名確率的リスク評価――は、原子力発電所における全体的検討過程において常に効果的に使われているとは言えない。フクシマは、そのことを如実に示す例である。大規模な津波を考慮に入れないことによって、日本は、評価の信頼性を高めるための十分な努力をしなかった。事故発生に続く数週間、日本政府は、確率的安全評価を早急に使うこと、そして、安全対策を改善することを約束した(これには安全性評価に基づく効果的な管理も含まれる)。これは、日本の安全規制を、もっとリスクに基づく、より効果的なものにするために必要である。そして、それは、「ゼロ・リスク」文化からの離脱を意味する。
冷却機能の確保
フクシマの事故が制御不能になっていったのには様々な理由がある。すべての原子炉の冷却機能が失われ、それが炉心溶融の危機をもたらしたのがその一つである。原子炉は、水の注入によって冷やされたが、炉心の損傷は防げなかった。電源が失われ、さらに、注入された水が漏れだしたからである。この同じタイプの冷却機能は、使用済み燃料の貯蔵プールにも適用されていた。
6月にIAEAに提出した報告書の中で、日本政府は、AC電源の回復まで、代替「最終ヒートシンク(最終的な熱の逃し場)」によって、原子炉と一次格納容器の代替的冷却機能を確保すると述べている。その実現方法は、代替的注水機能の多様化や、注入用の水源の多様化と増強、空冷システムの導入などである。
アクシデント・マネジメント(事故管理)対策の徹底
日本で最初の商業用原子力発電所は、1966年に送電を開始した。「シビア・アクシデント」3マネジメント対策――格納容器からの蒸気ベントや水素爆発防止などの措置――は、1992年まで導入されなかった。実際、アクシデント・マネジメントのための指針は、最初の構想以来再検討されていない。これらの対策は、法的な要求としては確立されず、事業者らによる自主的な取り組みとされた。
IAEAへの報告の中で、日本政府は、事故管理対策を、自主的な取り組みから法的要求に変えること、確率的安全評価のアプローチを使って策定することを約束している。これは、原子力産業のアクシデント・マネジメント対策がオープンでもっと透明なものとなることを意味する。
シビア・アクシデントへの対応
事故の大きさと、関連機関が事故発生下で対応した複雑な環境からすると、東電の運転チームの努力は、このようなストレスの大きい状況下で予測されるものとしては上出来だったのだろう。しかし、原発で起きたことは、全く逆だった。三つの炉心の溶融と、おそらくは4基での水素爆発。事故は、原子力史上最悪のものの一つと見なされることになった。
安全な原子力の世界で前進するには、非常に技術的な教訓が学ばれなければならない。如何にして水素爆発を防ぐか、如何にして格納およびベント・システムを強化するか、そして、如何にして、緊急事態対応能力を高めるかというものである。
水素爆発の防止
おそらくは、水素の燃焼によって4つの爆発が地震・津波の後数日内に起きた。1回目が、日本時間3月12日の午後3時36分に1号機で。2回目が、3月14日午前11時01分に3号機で。翌3月15日に、爆発音と、2号機のサプレッション・プールで計測された放射線レベルの上昇とにより、政府当局は、もう一つの爆発が起きたと推定した。これは、まだ確認されていないが、これにより大量の放射性物質(ガス、エアロゾール、汚染された水)が環境中に放出された可能性が疑われている。同日、もう一つの予想外の爆発が4号機であり、原子炉建屋が損傷し、壁が破壊された。この爆発の原因は確認できていないが、3号機で発生した水素が排気管などを通じて4号機に入り込んだのではと推測されている。
可燃性ガス濃度制御系――可燃性ガスの濃度を爆発限界下限以下に保つ役割を持つ――は、日本では、1992年に導入された。しかし、このシステムは、原子炉建屋の内部での水素燃焼を防ぐようには設計されていなかった。
IAEAへの報告書において、日本政府は、原子炉建屋内における水素爆発の防止策を強化する計画を表明した。この計画に基づく緊急事態対応策として、原子力・安全保安院は、原子炉建屋から水素ガスを放出するための対策を講じなければならないと発表した。たとえば、圧力を下げるためのベント用の穴をあけるというものである。事故の際、事業者は、シビア・アクシデントにおいて格納容器ベント・システムの操作に問題があることに気づかされた。具体的にいうと、システムを電源喪失状態で操作できるようには設計されていなかったのである。つまり、手動ということである。さらに、環境中に放出された(ベントされた)空気からの放射性物質の除去が不十分なことが判明した。従って、非常用ベント・システムは、もっと操作しやすく、もっと効果的なものにしなければならない。
緊急事態対応策の強化
事故発生直後、福島原発の雰囲気は、決して平静でも穏やかでもなかった。中央制御室における放射線被曝線量が高まり、運転員らは一時的に入室禁止となった。電源喪失は、暗闇を意味した。そして、コンピューターも電話線も死んでしまった。水位や圧力、温度などを測定する機器もうまく機能しなかった。そして、ロジ的な支援――追加のバッテリーや電源の発電所外からの輸送など――も地震と津波が起こした道路および車両の損傷のために、満足のいくものにはならなかった。緊急事態用補給品や機器を提供できる救援チームを動員するのは非常に難しかった。要するに、シビア・アクシデント対策が効果を上げられなかったということである。
となると、日本政府が、対応策の向上、とりわけ、スタッフ用の訓練と機器(よりよい測定計器)、よりよい放射線防護、それに、よりよいロジ的サポート・システムなどを約束したのは、不思議ではない。だが、日本政府は、この目的をいかにして達成するかについては具体的に述べていない。
国の原子力緊急事態対応体制
日本政府は、事故の後に原子力政策を見直した経験を持っている。1999年に東海村で起きた原子力事故(JCO臨界事故)は、地域住民の避難をもたらした日本で初めてのものだった。この事故の後、日本政府は、基本的組織構造、責任分野、簡素化されたプロセスを確立するために、原子力災害対策特別措置法を制定した。この法律によって、重大な原子力事故が起きた場合、官邸に国の原子力災害対策本部が設置されると同時に、各地の原子力施設の近くの指定されたオフサイトセンターで原子力災害合同対策協議会が活動を始めることになった。
3月、電源喪失と地震による損傷のため、福島原発の近くに設置されていたオフサイトセンターは、機能しなかった。このため、センターは、福島県庁に移動した。東電本店と福島原発の間には十分な直接的コミュニケーションがあった。しかし、他のコミュニケーションにおいては信じられないほどの困難があった。例えば、データがファックスで、しかも手書きで送られた。これが、国の対応の遅延と混乱を悪化させた。
3月以来、日本政府は、緊急対応本部や現地のセンターの場所として、もっと事故の影響を受けにくい場所を定めるとともに、ロジ面および関連機関の間のコミュニケーションの改善ができるよう法律を改定する必要を示唆している。政府はまた、原子力事故と巨大な天災の同時発生のような複合緊急事態に対応するためにそのシステムを再検討するとしている。これには、コミュニケーション手段、装置、このような緊急時に必要な補強品や機器を手に入れるチャンネル――迅速で効果的な対応をする上で重要な差をもたらす――が必要となる。しかし、これらの措置に加え、注意すべきことがいくつかある。原子力関連組織間のコミュニケーション、公衆への情報提供、国際的援助、環境モニタリングおよび予測などである。
役割分担の明確化とコミュニケーションの強化
フクシマの事故から数日のうちに、国と地方の緊急事態対応センター間、国と東電、そして、日本政府内の関連機関の間などにおいて、責任が明確に規定されていなかったことが明らかとなった。責任分担システムが確立されていないまま、地震と津波が福島原発とその周辺を襲い、その結果、信じられないような混乱と誤解が生じた。原子炉冷却のための海水注入のような決定的に重要なことでさえ、誤解があった。東電は、国の緊急事態対応本部では臨界についての懸念のため海水注入にためらいがあると理解していたが、国の本部の方は、このような疑念を表明したことは一度もないとしている。最終的には、現場の緊急対応担当の職員らが、承認を待たずに海水注入を行った。
フクシマの事故発生から3ヶ月のうちに、日本政府は、関連機関の役割と責任について再検討し明確化すると発表した。関連機関内および関連機関間のコミュニケーションと情報共有を改善する措置を具体的に示すというものである。
国民へのコミュニケーションの強化
福島県外の住民にとって、政府および東電によるコミュニケーション不足は大きな問題だった。例えば、放射性物資が健康に与える影響――具体的には「国際放射線防護委員会(ICRP)」が設定した放射線防護指針――は、住民・市民が必要とするもっとも重要な情報である。しかし、これについて事故発生後十分に説明されなかった。度重なる記者会見において、政府は、しばしば、「直ちに健康への影響はない」と述べ、混乱をもたらした。長期的にどのような影響が待っているのか定かでなかったからである
日本政府は、これは容認できることではないとし、IAEAへの報告書の中で、住民・市民に対し事故状況と対応についての情報を提供し、放射線の影響に関する適切な説明を行うことに関し、規則を強化すると約束している。
国際的反応に対する準備
地震と津波が日本を襲った直後から、国際社会は反応を示し、災害救助、原子力の専門技術、原子炉機器などの提供を申し出た。問題は、日本がこれに適切に対応できなかったことである。原因は、日本側に、このような援助の申し出を扱う事務局が存在しなかったことにある。国際社会とのコミュニケ―ションも常に十分というわけではなかった。それは、低濃度放射能汚染液を隣国に即時、適切な通知をしないまま、海に放出してしまったことに顕著に表れていた。政府は、今後はより早くまた正確な情報を通知できるよう国際情報通知システムの改善を約束した。
環境モニタリングの改善
放射性物質の放出源情報があまりにも少ないために、「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI:スピーディ)」――放出後の放射線被曝線量予測を迅速に行い、避難について助言するためのもの――でさえ、放射線被曝線量を信頼できる形で予測できないのではないかと感じられた。しかし、SPEEDIを使って出された予測結果は、現在公表されつつあり、その被曝線量予測は、避難の決定の助けにするという目的を十分に満足させるものであったことが判明している。従って、振り返ってみると、予測結果を事故の当初から公表して良かったと考えられる4。
事故が長期化し、その深刻度が増していく中で、住民は、避難させられたり、長期間、屋内待避の勧告を受けたりした。最終的に、日本政府は、緊急時の許容線量を定めたICRP とIAEAの指針に従うことにした。これらの指針はまた、避難区域、避難準備区域を定めていた。最終的に、これらの指針に従い設定された防護区域の広さ――原発から半径20-30キロメートル――は、日本の法律で定められたもの――半径3-10キロメートル――より、相当大きなものとなった。
日本政府は、次のような対策のための計画を発表した――SPEEDIその他のシステムを効果的に活用し、シビア・アクシデント発生当初からデータや計画などを公表する方法を策定すること、信頼でき、そして、計画的な形で緊急時環境モニタリングを実施するための体制を作ること、また、避難区域を設定するための取り組みを強化し、原子力緊急事態における放射線防護のための明確な指針を定めること。
安全規制体制
ここで留意すべきは、緊急時における市民の安全が意図的に無視されたのではないという点である。そうではなく、混乱を呼ぶ、過度に官僚的なシステムが、メッセージを伝える責任が誰にあるのかという点についての理解を曖昧にしてしまったのである。例えば、原子力・安全保安院――経済産業省に所属――は、安全規制に責任を持つ。だが、経産省は、原子力を推進するエネルギー政策の策定に責任を持つ。原子力安全委員会――内閣府に所属――は、原子力安全保安院の活動を監督(ダブルチェック)する責任を負う諮問機関である。そして、地方政府や日本政府の各省は、緊急事態の環境モニタリングに責任を負う。複雑で分かりにくい?その通りである。
日本政府は、このシステムを簡素化し、原子力・安全保安院を経産省から分けることを発表し、各省庁のうち、どこが原子力の安全性と環境モニタリングに責任を負う中心的機関となるべきかについて検討を始めている。これは、原子力安全規制体系の改定に繋がる可能性がある。日本の安全規制体系は、事故発生以来、複雑過ぎて、効果的でないと見なされている。IAEAへの報告書において、日本政府は、IAEAが規定した原則を使い、原子力の安全確保に欠かせないものとして、深層防護の追求という原則に戻ることによって、日本の原子力安全文化を改善するとしている。5
システム全体のインフラ強化は、直ちに検討しなければならないものだが、新しいシステムが構築された段階で対処しなければならない緊急の課題がある。法的構造および指針の強化、原子力分野の人材強化などである。
法体系・指針の確立および強化
日本政府は、既存の施設の高経年化に伴う劣化に対する対策について再検討しなければならない。また、新しい知見・経験(例えば、地震・津波専門家の発した警鐘)を取り入れなければならない。政府は、新しい法規に基づく技術的要求を明確にすると発表している。これには、いわゆるバックフィット(既存の施設に新しい規制を適用すること)も含まれるだろう。政府はまた、関連データを提供することによって、IAEAの安全基準改善に貢献する意向を表明している。
人材の維持・強化
日本における原子力の将来の如何に関わらず、日本が原子力関連の能力を持った人材を維持しなければならないことは明らかとなっている。福島だけでなく、全国の既存の施設やオフサイトセンターでの安全を確保しなければならないからである。このような原子力産業人材育成においては、環境のクリーンアップや住民の安全の確保にも努めなければならない。政府は、原子力事業者や規制機関の人材育成活動を強化するとしているが、この計画を遂行するに当たってどのような戦術を使うかは明確にしていない。
将来を見据えて
フクシマ事故の長期的影響は現段階では分からないが、日本の原子力計画に対する短期的影響は、すでに、相当重大なものとなっている。原子力委員会――原子力政策全般(原子力の安全性を除く)に責任を持つ諮問機関――は、国民に与える影響を考え、事故発生後1ヶ月以内の時点で[4月5日]、声明を発表し、その中で次のように述べている。「原子力委員会は、この事故を我が国のみならず諸外国においても原子力の安全確保の取組に対する信頼を根本的に揺るがすものとして、極めて重く深刻に受け止めております。」(原子力委員会, 2011a)
マスコミ各社が行った最近の世論調査によると、日本人の74%が、原子力の「段階的廃止」か「即時閉鎖」に賛成している。(朝日新聞、2011)
日本には運転許可を得ている商業用原子炉が54基あるが、そのうち、運転されているのは18基だけである(14基が地震のために運転停止、22基が定期検査その他の技術的理由により運転中止中)。2011年5月6日、菅直人首相は、中部電力に対し、新しい津波対策が講じられるまで浜岡発電所の運転を停止するよう要請した。それ以来、現在運転停止中の原子炉の運転再開は、さらに難しくなっている。日本政府は、欧州連合で導入されたのと似た「ストレステスト」を導入した。これによって原子力の安全性に対する国民に信頼を得ようとの考えである。
このように福島第一の原子力危機は続いている。今後、多くの技術的、社会的、法的、経済的障害を乗り越えなければならない。技術的に言うと、原子炉の安定化と大量――10万トン以上――の汚染水の管理が、未だに、重大な課題となっている。サイトの除染――事故で汚染された瓦礫を含む――も、極めて大きな課題である。加えて、ディコミショニング(廃炉措置)、それに、貯蔵プールに置かれた使用済み燃料と原子炉内にある損傷した燃料の取り扱いという長期的な課題がある。
この危機は日本だけではなく、原子力を導入しているすべての国にとっての教訓を示しているということを繰り返しておいて良いだろう。危機は、苦悩に終わる必要はなく、好機とすべきである。福島は、原子力災害の犠牲となった。しかし、それは、復興の象徴となることもできる。
謝辞
本稿は、福島第一原子力発電所で2011年3月に起きた原子力災害に関する特集の一部である。特集の編集および翻訳は、Rockefeller Financial Servicesからの助成金によって可能となった。
翻訳 田窪雅文
参考文献
朝日新聞 (2011) 世論調査, 6月13日
http://www.asahi.com/national/update/0613/TKY201106130401.html
石橋K( 1997) 「原発震災-破滅を避けるために」, 『科学』, 10月
日本原子力委員会( 2005) 『原子力政策大綱』
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/tyoki/taikou/kettei/eng_ver.pdf
日本原子力委員会 (2010) 『2009年原子力白書』第1章
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho2009/wp_c.pdf
原子力委員会 (2011a) 『 東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故と当面の対応について(見解)』, 4月5日
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/seimei/110405.pdf
原子力委員会 (2011b) 『東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に関する当面の対応について(見解) 』5月10日
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/seimei/110510.pdf
総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会地震・津波、地質・地盤合同WG(2009), 6月24日
http://www.nisa.meti.go.jp/shingikai/107/3/032/gijiroku32.pdf
日本政府原子力災害対策本部 ( 2011) 『 原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書-東京電力福島原子力発電所の事故について』http://www.kantei.go.jp/foreign/kan/topics/201106/iaea_houkokusho_e.html
1 多くの政府から提供された惜しみない援助や世界中の著名な専門家から寄せられた助言について、心からの謝意を表明したい。
2 本稿は、政府の報告書その他の公開情報に基づく筆者の個人的見解である。
3 シビア・アクシデント(過酷事故)とは、設計基準を超える種類の事故で、原子炉の制御にとって極端に難しい問題をもたらし、場合によっては炉心損傷または炉心溶融を招来するものを言う。
4 フクシマの事故発生後、地方自治体が各地域の環境モニタリングの責任を負っている。地震・津波により計器・施設が損傷しており、事故発生直後は、適切な環境モニタリングは、不可能だった。
5 政府は、「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」(委員長:畑村洋太郎)を、独立、透明、徹底という三つの基本原則の下に設置した。委員会は、年内に中間報告をまとめる予定である。
Together, we make the world safer.
The Bulletin elevates expert voices above the noise. But as an independent nonprofit organization, our operations depend on the support of readers like you. Help us continue to deliver quality journalism that holds leaders accountable. Your support of our work at any level is important. In return, we promise our coverage will be understandable, influential, vigilant, solution-oriented, and fair-minded. Together we can make a difference.
Topics: Nuclear Energy